映画館といえば「ポップコーン」。
でも、そもそもなぜ映画を見るときにポップコーンを食べる習慣があるのでしょうか?
気づけば定番になっているけれど、理由を知らない人も多いはず。
この記事では、アメリカで始まったその歴史から、日本の映画館に定着した経緯まで、わかりやすく解説します。
映画館でポップコーンはなぜ?いつから日本で食べるようになったの?
結論から言うと、映画館でポップコーンが定番化した理由は「安くて簡単に作れて、映画鑑賞を邪魔しない食べ物だったから」です。
そして日本では、戦後アメリカ文化とともに定着しました。
ポップコーンと映画館の関係はアメリカで始まり、トーキー映画の登場によって「映画中に何かを食べる」という文化が浸透し、その中で音も匂いも控えめなポップコーンが最適とされたのがきっかけです。
さらに、世界恐慌という厳しい時代背景も後押しし、手軽で原価が安く、映画館の収益になるポップコーンは経営的にも相性抜群な存在に。
やがてその文化が日本にも伝わり、今では「映画といえばポップコーン」が定着しました。
ここでは、ポップコーンが映画館に欠かせない存在になった理由と、日本で普及した時期を時系列で詳しく解説します。
ポップコーンが映画館で定番化した理由(アメリカ)
アメリカでは「音が静かで、安くて作りやすく、収益性も高い」ことから、ポップコーンは映画館の定番になりました。
そもそも映画館での飲食が広まったのは1927年、映像に音声がついた「トーキー映画」が登場してから。それ以前は無声映画の時代で、場内では生演奏が行われていたため、食べ物を持ち込むのはマナー違反とされていました。
しかし、トーキーが登場すると「音があるから、多少咀嚼音がしても問題ない」とされ、スナックの販売が始まります。
その中でポップコーンが選ばれた理由は3つ。
- 食べる音が小さい
- 原価が安い
- 簡単に大量生産できる
さらに、時代背景として1930年代の大恐慌の影響も大きかったです。
失業率が高く、消費が落ち込む中でも、5〜10セントのポップコーンは庶民にとって手が届く「ささやかなぜいたく」でした。
また、映画館側にとってもメリットは大。
チケット代は配給会社と折半されるため、ポップコーンなどの売店収益は劇場の純利益になり、経営を支える重要な収入源となりました。
今では全米の大手チェーン「AMCシアターズ」では、売店売上が全体の3分の1を占め、その中でもポップコーンは最大の稼ぎ頭。
売上の80%以上が利益という高収益商品なのです。
こうして「映画館でポップコーン」は文化として深く根付き、現代まで続いています。
ポップコーンが日本の映画館に普及したのはいつ?
日本では戦後アメリカ兵によって紹介されたのが始まりで、1957年から本格的に販売が始まりました。
第二次世界大戦後、アメリカ文化が日本に大量に流入しました。その中で、駐留アメリカ兵たちによって「映画×ポップコーン」のスタイルも紹介され、徐々に日本でも広まっていきます。
1957年には「マイクコーン」という会社が日本国内での製造・販売を開始し、ここからポップコーンは本格的に日本の映画館に定着していきました。
特に高度経済成長期には、「家族で映画館に行く文化」が広まり、ポップコーンも定番のおやつに。味は塩が主流でしたが、後にキャラメル味やバター風味などが登場し、バリエーションも豊富になりました。
そして、日本でも映画館にとってポップコーンは重要な収益源です。
チケットの売上の多くは配給会社に流れるため、映画館側が直接得られる利益は、パンフレットやポップコーンといった売店商品にかかっています。
映画館によっては「売店売上=劇場の命綱」と言われることもあるほど。静かに食べられて、ゴミの処理も比較的簡単なポップコーンは、唐揚げやアイスなどよりもトラブルが少ない食品として、今も支持されています。
このようにして、アメリカ由来の文化は日本でもしっかり根付き、映画体験の一部として愛されるようになったのです。
まとめ
ポップコーンが映画館の定番となった背景には、音が比較的静かで安価、さらに利益率が高く劇場の経営を支える存在であるという理由がありました。
アメリカから広まったこの文化は、日本でも戦後に定着し、今では欠かせない映画のお供です。
ポップコーンを楽しむことは、映画館を支える小さな応援でもあります。
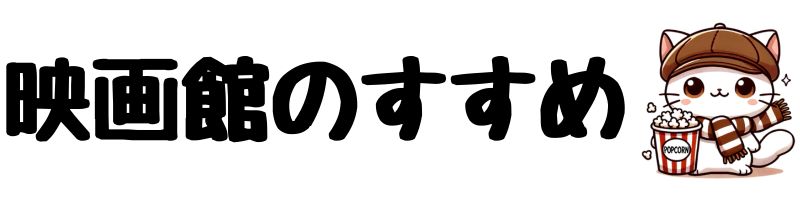










コメント